
- 工場勤務の将来性が心配、AIやロボットに仕事を取られないかな…
- 工場勤務の中でも将来性のある業種を知りたい
- 特別なスキルもないし家族のためにも、とりあいず今の工場で働くしかないよ…
このような悩みに答えます。
近年では、AIやロボット技術の進歩が毎日のようにニュースでとりあげられているのを目にします。
世の中がどんどん便利に安全になっていくのは非常に嬉しいことですが、同時に今まで人間がやっていた仕事がロボットに奪われてしまうのではないかと不安に思う人もいると思います。
とくに工場には多くのロボットがあり、これからもその数は増え続けると予想されます。
結論をいうと、工場勤務の将来性は明るくはありません。
しかし、業種によって将来性は大きく変わります。
現在、将来性に不安がある業種で働いている人や、子供の養育費やマイホームのことを考えた時に、今の工場勤務に不安を感じている人のために、収入をアップさせて、さらに安定した仕事を手に入れるための具体的アクションプランも解説しています。
本記事の信頼性
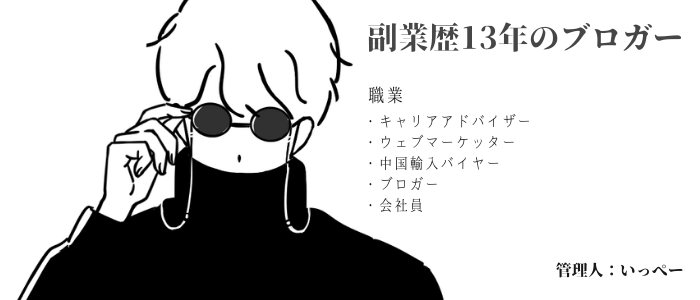
本記事の内容
- 工場勤務に将来性がない理由3選
- 工場勤務の中でも将来性がある業種
- 工場勤務の人が人生を逆転させるためのアクションプラン
それではいきましょう
目次
工場勤務に将来性がない理由3選

結論をいうと、工場勤務に将来性はありません。
もちろん「モノづくり」が無くなることはありません。しかし、これからの未来において、工場勤務の人の将来は決して明るいとはいえないでしょう。
その理由には以下の3つのがあります
AIやロボット技術の進歩
AIやロボット技術の進歩により、工場で勤務している人の仕事は徐々に少なくなるでしょう。危険な仕事や単純な作業はロボットの方がより効率よくできるため、そういった仕事をしている人の需要はこれから減っていくことが予想されます。
スキルが身に付かない
ここでいうスキルとは以下のようなものがあります
- ビジネスマナー
- コミュニケーション能力
- その他の専門スキル
これらのスキルは、会社の業績悪化などで転職する際にも有利なため、身につけておきたいスキルです。
しかし、工場勤務ではライン作業や単純労働が多く、これらのスキルが身につきにくいといえるでしょう。
夜勤など体力的にハード
工場勤務は基本的に給与水準が低いため、生活のために残業をすることが必須です。
必然的に労働時間が長くなり、会社によっては夜勤がある場合も多く体力的にハードであるといえます。
体力のある若いうちはいいですが、年をとってからのことを考えると将来性があるとは言いにくいでしょう。
現場に人は必要なのか?
AIやロボット技術の進歩により、人がおこなっていた作業が機械に置き換えられてきます。
会社としても、コストかけて機械を導入して、人の数を減らしていくほうが金銭的メリットが大きいからです。
しかし、人がいないと機械は動きません。なので、保守点検をおこなう人は必ず必要になりますし、人間でないとできない仕事も当然ありますが、全体を見ると人の数は減っていくことは容易に想像できます。
また、定年が65歳になるなど、これからは人生100年時代と言われ、年を取っても働かなくてはいけない状況になってきます。
まだ若いからと無理をしていると、結果的に将来にリスクを先延ばしにしていることになってしまいます。以上のことから工場勤務の将来性はあまり無いといえるでしょう。
工場勤務の中でも将来性のある業種

自動車関連
EV自動車など環境を配慮した車が増えることで、それにともなってエンジン関係の部門や会社は人員が削減されることが予測されます。
しかし、自動車業界全体でみると市場規模は約65兆円を超えており、自動運転など、これから大きな変革が起ころうとしている自動車業界は工場勤務の中でも将来性が高いと言えるでしょう。
3大鉄鋼メーカー
鉄の必要性はみなさんご存知だと思いますが、その中でも特に以下の
- 日本製鉄
- JFEホールディングス
- 神戸製鋼所
の将来性は安定しているといえるでしょう。理由は実質この3社が鉄鋼業界を独占している点があります。圧倒的に広い敷地と巨大な工場持っているため、ライバルは参入しずらく今後もこの3社の独占は続くでしょう。
ただし、職場環境はキレイとはいえないのでその点注意が必要です。
化学素材メーカー
繊維やプラスチックなどの化学素材の開発・製造をおこなっている化学素材メーカーは今後も安定しているといえるでしょう。
近年問題視されている、マイクロプラスチック等による環境汚染にも日本の化学技術は期待されており、海外への需要もますます高まっていくことが予想されます。
なので即戦力としては、文化や言語の違いがある海外でもリーダーシップや企画提案力、目標を周囲の人と共有し実行できる力を持っている人を求めているので転職の難易度は高めです。
精密部品関連
精密部品といっても下記のように様々なものがあります。
- 時計
- 計測機器
- カメラ
- 無線通信部品
など身近なものから専門的ものまであり、電子制御やソフトウェアで制御する機器のことを指します。
カメラなどは、スマートフォンの普及にともなって規模は縮小傾向にありますが、それ以外の例えば計測機器などは、5G向けの通信用測定器や電気測定器など需要の増加がますます期待できるでしょう。
工場勤務の人が人生を逆転させるためのアクションプラン

「工場勤務には将来性がないことが分かったけど、具体的にどう行動したらいいか分からない」という人のために大きく分けて分けて3つのアクションプランを紹介します。
アクションプラン1:給与とは別の収入源をつくる
工場勤務は基本給と呼ばれるベース給与が少ないことが多く、養う家族がいる場合や独身でも少し贅沢をしようと思ったら、残業をするしかありません。
しかし、残業や休日出勤ばかりしていると自分の時間が奪われてしまいますし、身体にも負担がかかってしまいますよね。
そこで、給与とは別に収入源を確保しておくことは健康面や将来のリスクヘッジのためにも非常に効果的です。
おすすめは以下のようなものがあります。
せどり
Amazonせどりが有名で、実店舗の商品の価格とAmazonでの価格差を利益とする方法です。
例をあげると
近所のお店で水筒がセール価格3,000円で売られていたとします。同じ水筒がAmazonでは6,000円で売られています。近所でこの水筒を買い、Amazonで販売した場合、6,000-3,000=3,000円となり、手数料や送料を差し引いても1,000円程度の利益を得ることができます。これがAmazonせどりと呼ばれるものです。
そのほかにも中国の巨大ECサイトであるアリババから商品を仕入れて、メルカリで販売する中国せどりというのもあります。
詳しくはこちらで解説しています>>【メルカリ+中国輸入】初心者でも簡単!やり方を分かりやすく解説!
ブログ
ブログで商品やサービスを紹介して収入を得る方法もあります。
うまくいけば何もしなくても毎月収入を得られるのが利点ですが、その分難易度が高めです。
またGoogleのアルゴリズムの影響で突然収入が無くなることもあります。
じっくり腰を据えてやれる人にはおすすめです。
詳しくはこちらの記事も参考にしてみてください>>ブログを始めるべき理由と身につくスキルを解説
株の配当金
これができれば一番いいんですが、ある程度まとまった資金と株に関する知識が必要なため、もっとも難易度が高い方法と言えます。
優良な企業の株さえ買っておけば、何もしなくても配当金が毎年もらえるため、不労所得を得ることができます。
当然リスクもあるため、しっかりと勉強して取り組む必要があるといえるでしょう。
まずは、せどりから始めてみるのがおすすめ。
なぜなら、この3つの中でもっとも結果が出やすいからです。
大きく稼ごうとするとそれなりに資金が入りますが、月に数万円の利益を目指すのであれば、10万円ほどの資金が十分に達成可能です。
アクションプラン2:異業種への転職
工場勤務とは全く違う職業への転職は、もっとも抜本的な解決方法といえるでしょう。
理由は下記のようになります。
- 将来性のある業界で働ける
- 営業のような職種を選べば、基本的なビジネスマナーやスキルを学べる
- 給与アップを見込める
もっとも有効な現状打破の方法ですが、やはり異業種への転職はそれなりの覚悟もいります。
長年勤めた会社を退職して、心機一転、家族のため、マイホームのため、自身の市場価値を上げるため、転職してもいいと思える人には非常に効果的な選択肢でしょう。
退職、転職に関してはこちらをご覧ください
>>転職サイトと転職エージェントの違い【うまく使い分ける方法も教えます】
アクションプラン3:同業他社への転職
アクションプラン2よりは少し気持ち的なハードルは下がりますが、転職の難易度は上がります。
今の会社の技術や経験が活かせる工場に転職する方法です。
もちろん仕事内容は違うかもしれませんが、異業種への転職に比べると変化は少ないといえます。
現在の経験が活かせる場面もあるでしょう。
ただし、やはり大手のメーカーを狙っていくとなると、中途の求人が常に出ているとは限りません。
なので求人が出ているかどうかの、タイミング・運の要素も関わってきます。
日頃から常にアンテナを張っておいて、チャンスが来たらすぐに行動できるようにしておくことが大切といえるでしょう。
転職サイト、転職エージェントについてはこの記事を参考にしてみてください>>転職サイトと転職エージェントの違い【うまく使い分ける方法も教えます】
まとめ:自身の状況や将来を考えて行動することが大切

工場勤務の将来性が無いことは事実としてありますが、すぐに、例えば3~5年後にロボットによって仕事がなくなる可能性は考えづらいです。
人にしかできないこともありますし、ロボットの整備には必ず人が必要です。
労働環境や給与面、身に付くスキルなどを総合的に考えた結果、工場勤務の将来はあまり明るいものではないかもしれません。
最終的には、自身のライフプランや大切ことに合わせた、アクションプランをとることが大切といえるでしょう。